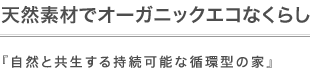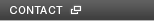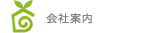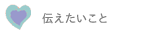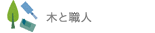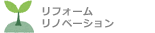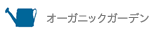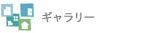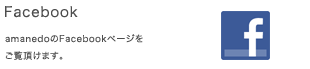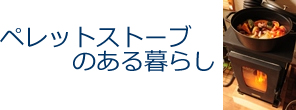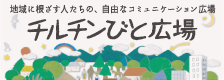日記
無垢の杉のダイニングテーブル
2015年6月8日


さいたま市の自宅で、リース教室をされている由美さんから、教室で使う無垢の杉の
ダイニングテーブルの相談を頂きました。
ダイニングテーブルは、くらしの中でも一番手や体が触れる場所。
食卓を囲む、くらしのど真ん中の役割の大切なものです。
無垢の杉のテーブルは、汚れや傷に強いウレタン塗装のテーブルとは感触も、香りも全く
異なります。
由美さん念願の杉の無垢のダイニングテーブルは、
限られたスペースを有効に使い、一人でもストレスなく簡単に移動ができて、大人数でも
対応できる。そんな条件をあれやこれやと思いを巡らし、
最終的にW1800XD450の細長いテーブルを二つ作成することになりました。
普段は、壁沿いの書類を収納しているカラーボックスを下部に収納し、教室の時には
簡単に取り出せる。という仕様で、使い勝手や大きさ・高さ・脚の位置も慎重に吟味しました。
由美さんは、天竜の月齢伐採・天然乾燥の榊原さんを通じて知り合いましたが、愛媛のご親戚
の無肥料・無農薬栽培の柑橘類を青山のファーマーズマーケットなどで、販売もしています。
もちろん味も抜群ですが、皮まで安心して食べられますから、お料理や、スィーツづくりなど、
100%生かすこともできます。
自らのアトピーの克服体験などから、化学物質の怖さや、本当に体に良いもの。快適なもの。
そして何より未来の子供たちに、ちゃんとしたものを残したい。っと真摯に活動されています。
リース作りのそのセンスの良さも抜群ですが、一人の女性・人間としてもとても魅力的な方です。
斉藤 由美さんの活動はこちらから > nature reason
昭和女子大学の建築学科に無垢の木の仕事を
2015年6月3日
私たちの材木屋さん小川木材さんの林場に、今年も昭和女子大学の建築科の方たちが来られました。
先生を筆頭に、皆さん伊東棟梁の説明を一生懸命聞いて頂きました。
今回は、四方蟻と言う今では珍しい刻み方も見ていただきました。
そして、お土産は片面はそのまま、片面はかんなでけずった、無垢材のプチまな板。
かんな削りの表面のすべすべ感、今まで感じたことのない感触、その違いににみなさん大感激!
今ではあまり触れる事の出来ない鉋仕上げ、機械とは一味もふた味も違う、職人ならではの仕事です。
デッキの素材選びは悩ましい
2015年6月1日

 デッキの素材選びはとても悩ましい。我が家の日曜大工で作って10年経たセランガンバツのデッキは、一部が腐食し穴があくほどになり、交換することにしました。
デッキの素材選びはとても悩ましい。我が家の日曜大工で作って10年経たセランガンバツのデッキは、一部が腐食し穴があくほどになり、交換することにしました。
今回は天竜の月齢伐採・天然乾燥の杉の角材をプロにお願いして、きちんとした施工で作ってみることにしました。油分が豊富な角材がどんなことになるかは、これから見守ることになりますが、今まではささくれ立って、素足で歩くことはできなかったセランガンバツのデッキでしたが、しなやかでツヤツヤの杉は裸足でもとっても気持ち良いことにびっくりです。
「くさりにくい。あるいはくさらない」それは確かに大切な条件ではありますが、
根絶やしになる程切りつくしてしまっている南洋材や、最終的には土に還らない、プラスチックの新建材のデッキ風という選択肢の他にも、
日々の暮らしを気持ち良く過ごし、最後は土に還るという素材の選択もありかな。っと
おそらく10年位もってくれるような気がします。
ちなみに今回は、塗装なしという選択肢もありましたが、大工さんのすすめにより、ロハスコートを塗りました。


天竜視察
2015年5月19日
5月12日天竜 榊原商店 TSドライシステムへ視察兼見学。
未来の林業男子と共に行ってきました。 とても楽しく充実した一日になりました。
榊原さんをはじめ商店の皆様、TSドライシステムの皆様、案内してくださり有難うございました。
古くから伝わる月齢伐採、天然乾燥を行う方たちとつながっていることにあらためて実感、感謝いたしました。

榊原商店
天竜T.S.ドライシステム協同組合

一発勝負 難しいみたいです。

T.S.ドライシステムの方から説明を受ける大工さんと未来の林業男子


推定1300年の杉の木
無垢を扱うという仕事 無駄とみるか余白とみるか・・・
2015年5月12日
 この写真のベンチは、無垢の杉の「端材」でつくりました。
この写真のベンチは、無垢の杉の「端材」でつくりました。
無垢材は、割れが入ったり、節があったり・・・
製材所さんも、そして大工さんも、それを見越して、余分をみます。
なので、結果的には結構な寸法の半端な材料がでます。
無駄が出ないように、きっちり。
という訳にはいかないのが、「余白」となって、こんな素敵なおまけができます。
工業系の住宅メーカーさんは、1円の無駄もださないように、きっちり、きっちり。だそうですが・・・
無垢を扱う職人の仕事だからこそ、こんな無駄を「素敵なおまけ」に変えられることも、悪くないです。
完成見学会 沢山の方に来て頂き有難うございました。
2015年5月7日
つつじが丘 S様邸 完成いたしました。
そして、完成見学会も無事、終了いたしましたので、その模様の一部を
写真にてご紹介します。たくさんの皆様、本当にありがとうございました!





完成見学会終了後 お施主様 主催 お疲れさん会をさせていただきました。
皆様、お疲れ様でした。 そして、建て主様有難うございました!


9月27日 東京で上棟式フルコース 建前・五色の旗・餅まき・木遣りやります!
2014年9月16日
建て主さん・山・設計者・職人たち。 みんなの顔がみえるすまいづくり

東京三鷹・つつじヶ丘・Sさまの家づくりの現場は瀬野和広+設計アトリエの設計監理のもと、
建て主さまの篤い想い、そして暖かいご協力を頂き、昔ながらの丁寧な木組み・人組み・心組みが進んでいます。
きたる、9月27日土曜日 13時~17時(随時)
天竜の月齢伐採・天然乾燥のツヤツヤの桧・杉の屋台骨に、
五色の旗・弓矢を掲げ、餅まき・木遣り。と上棟式のフルコースを開催いたします。
上棟軸組見学会には、多くの皆さまにも見て頂きたいと思いますので、皆さまお誘いあわせの上、
是非ご参加くださいませ。
上棟軸組見学会の詳細はこちらをクリック by瀬野和広+設計アトリエ
私たちも参加している天竜・山の応援団体です。
 |
 |
チルチンびともよろしくね
 |
 |
長老を囲む会 内田悟さんの出張やさい塾
2014年8月15日
少し人数の余裕がありますので、お知らせです。
今回の長老を囲む会は 東京築地御厨(みくりや)の内田悟さんをお迎えします。
こだわりの青果店の店主として人気の内田さんは本業に加え、わかりやすい講演で、ひっぱりだこの大変ご多忙な方ですが、今回ようやく長老を囲む会にお迎えすることができました。
レストラン等へ納品をする傍ら、一般の方にも安全・安心な野菜の選び方や扱い方を独自の視点でわかりやすく伝え、幅広い活動をされていらっしゃいます。
内田さんの野菜塾のページ http://www.yasaijyuku.com/
日時: 9/21(日) 13:00-15:00
場所: 樹木と菜園のあるエコな家
http://www.reformlab.jp/
東京都世田谷区下馬6-12-18
参加費: 大人4,800円、二歳以上のお子様3,000円。
(講演代、冊子、お茶、軽食が含まれます)
人数: 15名前後
お申込み・お問い合わせ:
メール:info@reformlab.jp
電話: 03-5787-8633 天音堂(あまねどう)・リフォームラボ あがり宛て
野草de フレンチ 野の草とフレンチのマリア―ジュ!
2014年7月11日
代沢・Bistroあおい食堂の加賀田京子さんと山梨・甲州市のつちころび、野草研究家の鶴岡舞子さんのコラボ企画に行ってきました。
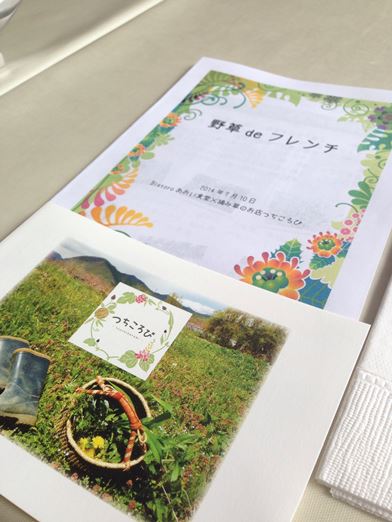
最近とっても、とっても気になる野草
誰からも水も肥料ももらわず、自らの力で根を張り、芽をだし葉をつけ花や種となり、そして種を残す。
そんな野草の生命力を美味しく頂く機会を頂きました。
野草の力は計り知れません。人を助けてくれる薬効をもちますが、その多くは毒を持ちます。
長い年月をかけ、先人の多くの犠牲の上に、野草とうまく折り合うことを積み重ねてきたのでしょう。
それらの知恵って宝です。
その宝を一人でも多くの人に知ってもらいたい、と笑顔が一杯の鶴岡さんは、野草研究家の活動をされています。
そして今回は、食のプロ 加賀田京子さんの手にかかった野草たち。
鶴岡さんが山梨でハンティングした野草たちは、今まで経験したことのない味として、主役にもなり、またスパイス・調味料として、その存在感と脇役感が見事でした。
野草のワイルドさとシェフの繊細な感性の、完璧なマリア―ジュは、素敵です。
写真のお料理は、
グリルチキンにヨモギのファルシをロールして煮込んだもの。
3種の野草・ギシギシ・葛の新芽・イタドリが苦味・酸味、そして様々な食感がソースに絡み、驚きの美味しさでした!

お寺はなぜ壊れない 木暮人職人倶楽部:・東大実験その2
2013年4月3日

昨年の3月から始まった、関東大震災で壊れなった建長寺の法堂の研究。
今回は試験体が壊れる限界までの実験を見学させていただきました。
6時間を超え負荷をかけて行く中で、実験データをみる先生が「なにこれ!」
と驚かれていらっしゃいました。、
それは一部が壊れても、また復元を繰り返しているという事でした。
かつての人工乾燥であるに違いない試験体がぽっきり折れてしまうのとは、様子が違うようでした。
試験体は天竜の天然乾燥の杉材です。
ここで安易に天然乾燥材や杉材の優位性を結論づけることは出来ませんが、何時間も試験体を見つめる
中で、メリメリと音を立てて一部が割れながら、靱のようなしなやかさで、もとに戻ろうとする杉。
油分が残っている繊維質の杉材ならでは粘り。を目の当たりにしました。
見学をしている人から、「これって日本人だよね。」という声も聞こえました。
試験体の製作は、職人の仕事です。
丁寧に手入れされた道具「のみ」や「げんのう」を使い、当たり前の仕事として仕掛けをつくった
大工職人が、そしてその後ろには道具をつくった職人がいます。
このことは、目の前にある事実です。
先人の知恵で培われた、職人の知恵、天然由来の無垢の木や伝統構法のすばらしさ。
ということに少しでも多くの方が関心を持っていただければと願います。
下の写真は、向かって右はけやき・左は杉の試験体。
同様の条件での実験ですが、けやきは固定するボルトのところまで、ばっかり割れています。
堅牢な材のけやきは、いったんダメージを受けると割れてしまうようです。

東大の藤田先生と研究室のみなさん 実験の見学をさせていただきありがうございます。
そして木暮人 職人倶楽部のみなさんでした。